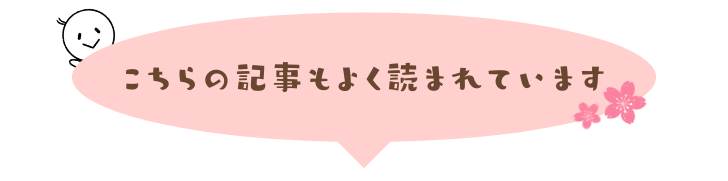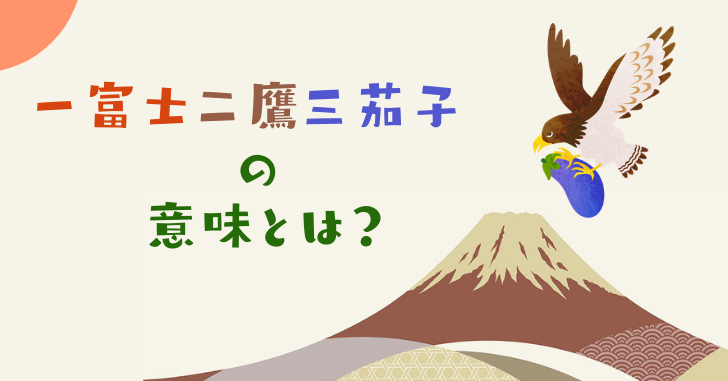私たちが普段見ているテレビ番組やスマホのニュースなどでは、事件や有名人に関する話題が上がり、それが人々の噂になることがありますよね。
しかし、いつの間にかそのような出来事は忘れさられ、話題に上がるということも無くなってしまいます。
このようなことから、古くから「人の噂も七十五日」という言葉が作られたわけですが、この七十五日とは、一体何が由来となり作られた日数なのでしょう。
そこで、この記事では、
- 人の噂も七十五日の意味
- 人の噂も七十五日の由来
- 人の噂も七十五日の反対の言葉と類語
- 人の噂も七十五日のような言葉は英語圏にもある?
について解説・紹介していきます。
人の噂も七十五日の意味とは?
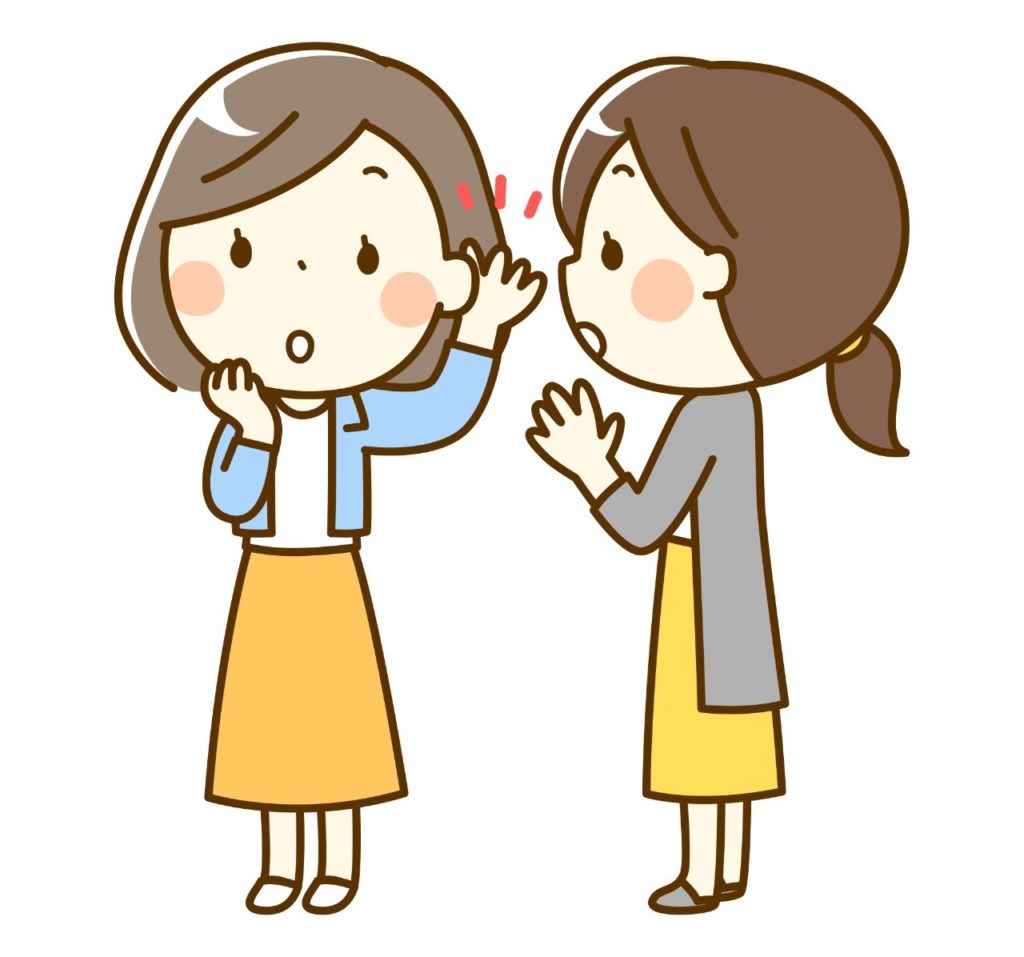
『人の噂も七十五日』という言葉は、「ひとのうわさもしちじゅうごにち」と読みます。
「ななじゅうごにち」ではありませんので注意して下さいね。
人の噂も七十五日は、
『世間で人が噂をしていても、それは一時的なものに過ぎず、やがて自然に忘れ去られてしまう』という意味のあることわざです。
自分が恥ずかしいことをしてしまったとしても、人の噂というものはそう長くは続きませんよね。
しばらく経てば消えていくものなので、このことわざには、『人の噂はそう大したことがないので、気にせずに放っておけば良い』という意味も込められています。
人の噂も七十五日の由来とは?
「人の噂も七十五日」が作られた由来としては、いくつかの説が存在しています。
季節が変われば人の話す内容も変わっていくという説

一般的に季節は春夏秋冬の4つで、「四季」と言われますよね。
しかし、旧暦や昔の東洋医学の考えでは、「土用(どよう)」という季節を加えた『五季(ごき)』という考えがあるそうです。
現在では「夏の土用」のみが認識されていて、他の土用の日は重視されていませんが、本来季節の変わり目である「土用」とは、『立春・立夏・立秋・立冬の日の前18~19日間』のことを指します。
ちなみに、2021年の土用は、下記のとおりです。
【冬の土用】 2021年1月17日(日)~2月2日(火)
【春の土用】 2021年4月17日(土)~5月4日(火)
【夏の土用】 2021年7月19日(月)~8月6日(金)
【秋の土用】 2021年10月20日(水)~11月6日(土)
一年の365日を5で割ると一つの季節は73日で約75日であると言えます。
このことから、七十五日は一つの季節を表すとされ、『一つの季節が過ぎる頃には人の噂も忘れられている』と言われるようになったという説になります。
農作業の作業期間を取り入れたという説
農作物は種を蒔いて収穫できるようになるまで、大体75日かかるそうです。
そのため、『農作物と同様に噂も種が蒔かれてから、収穫するくらいのうちに刈り取ってしまえる』という考え方から「人の噂も七十五日」と言われるようになったという説になります。
また、、農作物が育って収穫する時期になれば忙しくなるため、『同じことをずっと話してはいられないから』という説もあります。
語呂の良さで七十五になった説
「七十五日」が使われる理由として、「しちじゅうごにち」の『語呂が良いから』という説もあります。
100日のほうが区切りは良さそうですが、ことわざなどでは言い易さが重要となり、リズムが良いものは長く言い伝えとなって残ることが多いと言われています。
このように、七十五日となった説はいくつもありますが、残念ながらこれだと断定できるものではないようです。
人の噂も七十五日の反対の意味のことわざは?
「人の噂も七十五日」は、『人の噂はそう大したことがない』という意味合いで用いられているため、反対の意味としては、「人の噂はおそろしい」というような意味合いのことわざが該当します。
- 『虎狼より人の口恐ろし』
意味:虎や狼による被害なら防げるが、人の陰口や中傷は防ぎようがなく恐ろしい - 『悪事千里を走る』
意味:悪い行いはたちまち世間に知れ渡ってしまう
「人の噂はずっとなくならない」などといった類のことわざは見つかりませんでしたが、この2つのことわざは、噂が無くなるまではなかなか辛い期間になることを表しています。
人の噂も七十五日の類語は?
言い回しが少し違うだけで、「人の噂も七十五日」とほとんど同じ意味のことわざも他にあるようです。
- 『善きも悪しきも七十五日』
- 『世の取り沙汰も 七十五日』
まれに勘違いした使い方として「人の噂も四十九日」と言ってしまう方がいらっしゃるようです。
しかし、一般的に「四十九日」というと、仏教の「命日から数えて49日目に行う追善法要」のことを指します。
噂話とは関係のないことなので間違えないようにしましょう。
意味合いは違いますが、『初物七十五日(はつものしちじゅうごにち)』ということわざもあります。
「 初物七十五日」には、『縁起が良い初物を食べると寿命が 七十五日延びる』という意味があります。
このように「七十五」という数字は、色々なことわざで使われています。
-

初物とは?七十五日の意味と長生きの理由、食べる方角について詳しく解説!
日本では、「初物を食べると縁起がいい」と言われ、初競りでは、毎年驚きの値段で取引され、中には「ブドウ1房に100万円以上 ...
続きを見る
人の噂も七十五日と同じような表現は英語圏にもある?
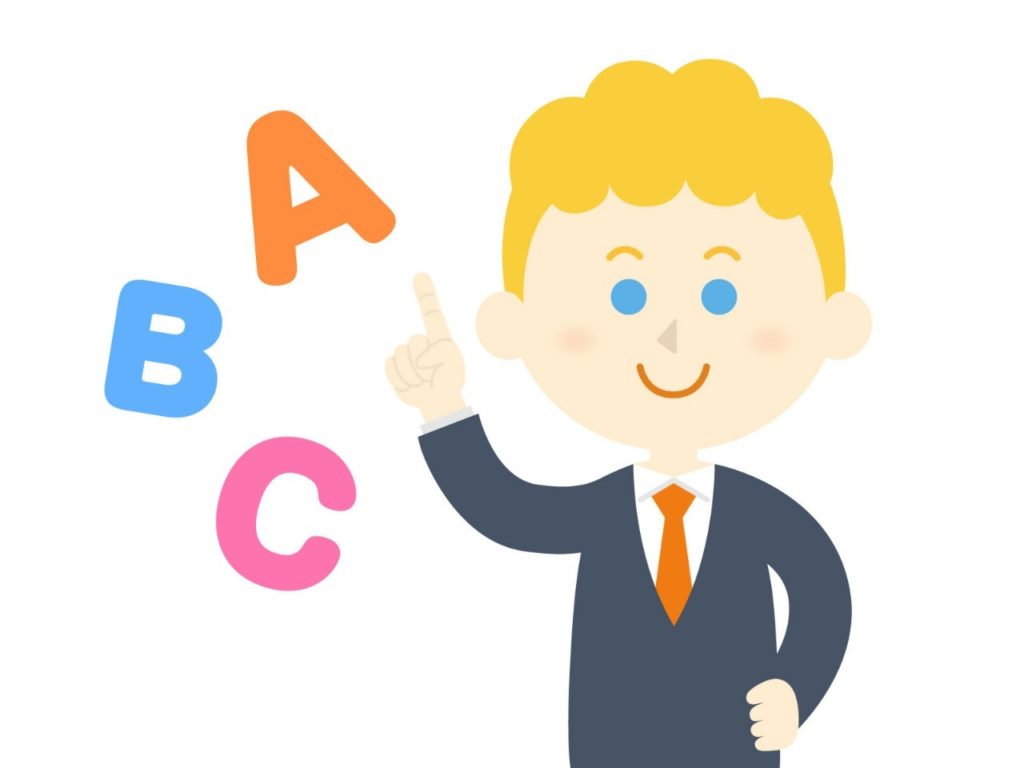
「人の噂も七十五日」のような英語で使われることわざでは、『A wonder lasts but nine days.』というものがあります。
last は「続く」という意味を持つ動詞です。
したがって、意味は「驚いたことも9日しか続かない」や「不思議がるのも9日だけ」という訳になります。
それにしても9日というのは、日本の75日と違いかなり短いですよね。
しかしながら、これには理由があるようです。
英語圏で多いキリスト教のカトリックでは、9日間を区切りにする祭事が多くあり、それが終われば日常に戻ることから9日になったと言われています。
また、生まれた子犬が目を開くまでが約9日間とされ、その間は人々が気にかけて注目しているからという考えもあるそうです。
まとめ:人のうわさは気にせず 放っておくのが一番
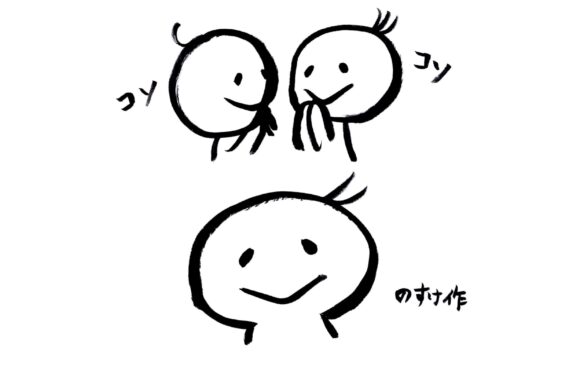
- 人の噂も七十五日は、世間で人が噂をしていても、一時的なものに過ぎず、やがて自然に忘れ去られてしまうという意味があることわざ
- 七十五日の由来は、いくつかの説が存在する
- 人の噂も七十五日の類語は、「善きも悪しきも七十五日」・「世の取り沙汰も 七十五日」
- 英語圏でも、類似したことわざがある
いかがでしたでしょうか。
文献では、1833年に初編が刊行された『春色辰巳園(しゅんしょくたつみのその)』という本に、「人の噂も七十五日、過ぎたむかしは兎も角も」という記述があるそうです。
つまり、江戸時代にはこのことわざは確立していたようです。
また、ビジネスの世界では「3対33の法則」というものがあると言われ、
これは「商品に満足した人は3人に話をし、不満を持った方は33人に話をする」というものです。
つまり、悪い噂は良い噂の10倍の速さで広まるということになります。
個人的に私は他人の噂など気にせず、自由に生きたいと思うタイプですが、できるのであれば、噂の種を蒔かずに穏やかに過ごしたいものです。
ここまでご覧いただき、ありがとうございました。