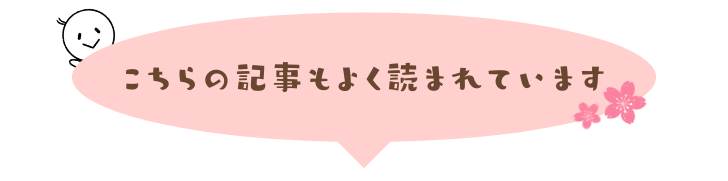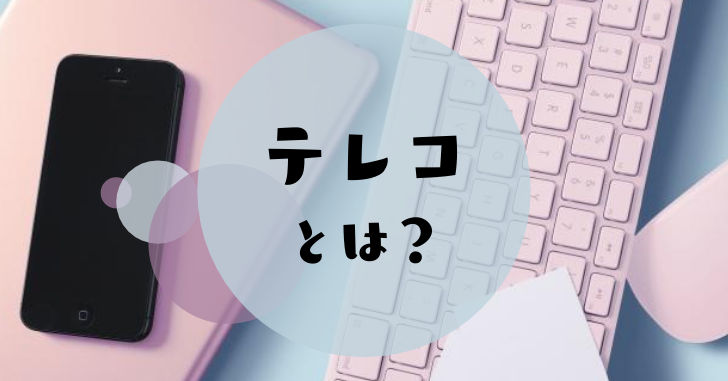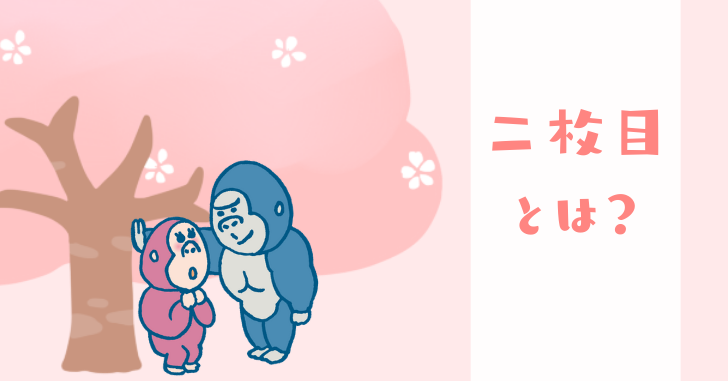皆さんは、「テレコ」という言葉をご存知でしょうか。
カタカナなので「何か英語の略称かな?」と思われるかもしれませんが、実は正式な日本語として用いられている言葉になります。
関西の方は分かる方が多いと思いますが、関西以外の方はあまり聞いたことの無い言葉となっていますので、「テレコ」の意味について紹介していきたいと思います。
そこで、この記事では、
- 「テレコ」の意味や由来
- テレコの使い方【例文】
- テレコの類語・言い換え表現
について解説していきます。
テレコの意味とは?

「テレコ」とは、「互い違い」や「あべこべ」、「入れ違い」などの意味があります。
主に関西の方言として使用される言葉となっていますが、『ビジネス用語』としても使用されています。
また、「テレコ」の漢字表記はなく、カタカナで表記されるのが一般的です。
では、「テレコ」の語源とはいったい何なのでしょうか。
テレコの語源は歌舞伎用語だった?
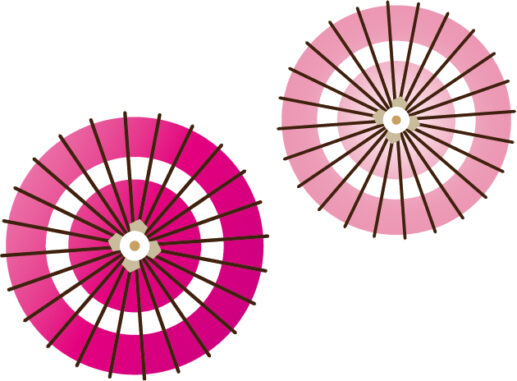
元々「テレコ」は、歌舞伎の世界で使用されていた言葉だと言われています。
歌舞伎の舞台で一つの演目を行う際、二つの筋書きを一幕おきに交互に行っていくことを「てれこ」と言っていたそうです。
例えを使用して詳しく説明すると、一つは宮本武蔵の生い立ち、もう一方は佐々木小次郎の生い立ちを描いているとします。
武蔵の話の一部が終わると幕を下ろし、次は小次郎の話で始まるといった形で、交互に話を展開していくことを言います。
また、歌舞伎用語として使用する場合は、ひらがなの「てれこ」で書かれるのが一般的です。
語源ははっきりと分かってはいませんが、次の二つの説が言われています。
「手入れこ」説
手を加えるという意味がある「手入れ」に、接尾語である「こ」が付いた言葉である「手入れこ」が次第に「てれこ」となっていったという説になります。
接尾語の「こ」は、「かわりばんこ」や「駆けっこ」といった言葉にも使われています。
「略称」説
「人の手を入れて交互(こうご)にする」が省略され、「てれこ」となった説になります。
ちなみに、カセットテープのA面とB面を取り間違えることから、「テープレコーダー」の略称である「テレコ」が語源になったという説もありますが、こちらは俗説とされています。
最初は歌舞伎用語として使用されていた「てれこ」ですが、次第に芸人用語としても使用されるようになり、世間一般でも使用されるようになったと言われています。
では、実際に「テレコ」を使った文章を見ていきましょう。
テレコの使い方やビジネス例文の紹介

「テレコ」は様々な使われ方をしていますので、例文で「テレコ」の使い方を確認していきましょう。
日常生活偏
- 上下逆さま
「朝、目が覚めると、テレコになって寝ていた」 - 裏表
「洋服がテレコになってるよ」 - ちぐはぐ・あべこべ
「会社に着いてから靴下がテレコになっていることに気がついた」
ビジネス偏
- 入れ違い
「A社への納品分がB社へ納品されてテレコになってしまっていた」
「A社へ向かうと、上司とテレコで到着し、既に謝罪が終わった後だった」 - 順番が違う
「この資料の3ページ目と4ページ目がテレコになっていますよ」
テレビ業界偏
- 交互に
「A番組とB番組を毎週テレコで放送する」 - 入れ替える
「Aの台詞をBの台詞とテレコにして」
ファッション業界偏
- コーディネートが合っていない時(あべこべな時)
「このコーディネート、テレコでしたか…」
といったように使用します。
しかしながら、「テレコ」は口語(話し言葉)の要素が強い言葉となっていますので、文章では他の言葉に置き換えて使用するようにしましょう。
また、アパレル関係では「テレコ素材」と呼ばれる凹凸が出るようにリブ編みされた生地があり、互い違いに凹凸になっていることからその名前が付けられています。

テレコの類義語・言い換え表現は?

「テレコ」の使い方を見てみると、たくさんの意味があることが分かりますよね。
そのため、「テレコ」と同じ意味を表す類義語は、使用する場合によって変わってることになります。
「互い違い」・「あべこべ」・「入れ違い」などなど・・・
残念ながら「テレコ」とまるまる置き換わる特殊な言葉は存在していません。
「テレコ」の意味を理解することで言い換えができるようになります。
まとめ:「テレコ」は様々な業界で使用されるビジネス用語だった
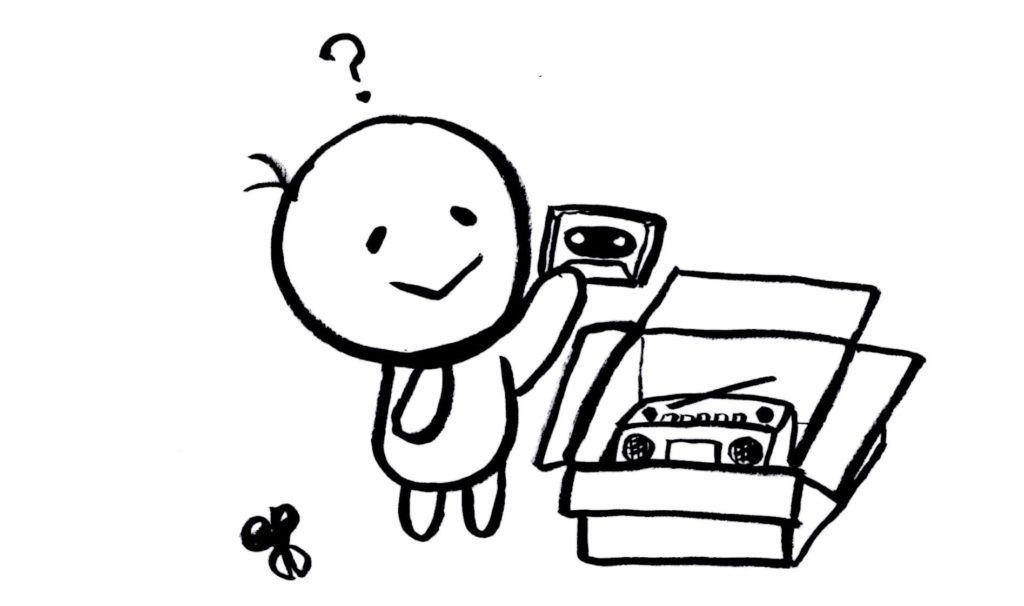
- 「テレコ」には「互い違い」・「あべこべ」・「入れ違い」など様々な意味がある
- 歌舞伎用語として使用されていた「てれこ」が由来となっている
- 「テレコ」は口語的要素が強い言葉となっている
いかがでしたでしょうか。
「テレコ」は、業界によって様々な使い方をすることが分かりました。
関西の方は使い慣れた言葉かもしれませんが、今まで聞いたことも使ったこともないという方は、慣れるまでは意味を理解しにくい言葉かもしれませんね。
ちなみに、歌舞伎から生まれた言葉はたくさんあり、「世界」・「ノリ(音に乗る)」・「なあなあ」も歌舞伎が由来となっています。
また、芸能界では朝夕関係なく「おはようございます」と挨拶を交わすのですが、これも歌舞伎の風習からきたものという説があり、その当時の風習が残ったものとされています。
江戸時代にはまだ照明器具がなく、歌舞伎の公演は主に明るい時間に行われていました。
早朝入りする役者さん達へのねぎらいの言葉として、「お早いお着き、ご苦労様です」が由来になったと言われています。
ここまでご覧いただき、ありがとうございました。