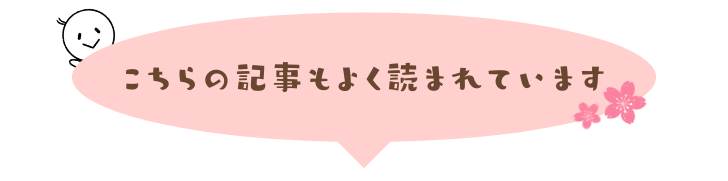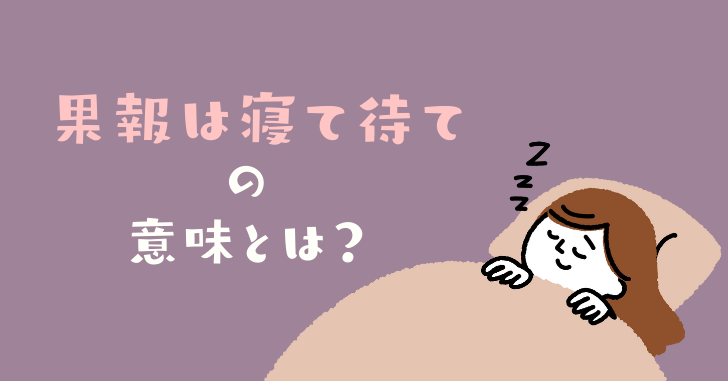皆さんは、「果報は寝て待て」という「ことわざ(慣用句)」をご存知でしょうか。
聞いたことがあると思っても、「果報」の意味が分からなかったり、ことわざ自体の意味もよく理解していなかったりすることが多い言葉のようです。
また、実際に誤った意味で使用している方も多いと言われています。
そこで、この記事では、
- 「果報は寝て待て」の意味や由来
- 「果報は寝て待て」の使い方【例文】
- 「果報は寝て待て」の類語・対義語
- 「果報は寝て待て」の英語表現
について解説・紹介していきます。
「果報は寝て待て」の意味とは

「果報は寝て待て(かほうはねてまて)」ということわざには、
『幸運の訪れは人間の力ではどうすることもできないのだから、焦らずに時機を待つのが良い』
という意味があります。
果報は家宝ではありませんので、注意しましょう。
また、「運は寝て待て」や「福は寝て待て」と言われることもあります。
幸運を得るには、寝て待つ前に行動が必要
「果報は寝て待て」と聞くと、幸運がやって来るのを寝て待つしかないと思ってしまいますが、「果報は寝て待て」という言葉には、
『やれることを全てやった後は、良い結果が訪れるのを気長に待つしかない』という意味が込められています。
決して、「(何をしなくても)いつか幸運が訪れる」という意味ではないことに注意してください。
「果報は寝て待て」の由来
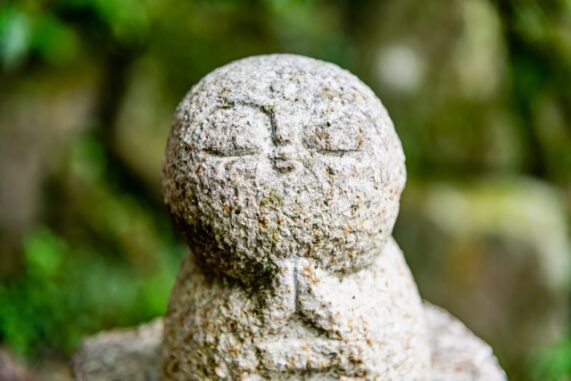
「果報は寝て待て」の「果報」とは、
『前世での行為(善行・悪行)によって、現世で報(むく)いとして受けること』という意味がある仏教用語になります。
※報いとは、ある行為の結果として自分の身に返ってくる事柄のことです。
「果報は寝て待て」ということわざは、仏教思想が由来となって生まれた言葉になります。
仏教では「輪廻転生(りんねてんしょう)」という、命あるもの全ては生死を何度も繰り返し、新しい生命に生まれ変わり続けるという思想があります。
現在幸せであるのならば、前世で善い行いをしたことが現世で報いとして返ってきているというわけです。

善いことをすれば、その結果として未来に善いことが返ってくるし、悪いことをすれば、その結果として未来に悪いことが返ってくるということだね!
また、「果報」と似た言葉で、「因果応報(いんがおうほう)」という言葉もありますが、こちらも仏教思想の一つで『自分が行った行為(善行・悪行)によって、その報いの結果がもたらされること』を意味する四字熟語になります。
仏教思想では、「果報」も「因果応報」も、どちらも幸運・不運の意味を持っていますが、一般的には「果報」は『幸運なこと』、「因果」は『不幸なこと』を意味する言葉として扱われています。
「果報は寝て待て」という言葉には、
『努力を尽くしたのであれば、(いずれその結果がやってくる)あとは自然にまかせ、静かにその時を待つのが良い』という意味があるのです。
「果報は寝て待て」の使い方【例文】

では実際に、「果報は寝て待て」を使った例文をいくつか見てみましょう。
ポイントとしては、『努力の結果を気長に待つしかない』という意味で使用するということです。
相手に用いる場合は、「励ましの言葉」として用いることができます。
- もうやることはやったんだから、そんなにくよくよするなよ。果報は寝て待てと言うだろう。
- 試験は終わったことだし、果報は寝て待てだ。今からパーッと飲みにでも行くか。
- みんなよくここまで尽力してくれた。あとは果報は寝て待てで上手くいくことを祈るだけだ。
- 果報は寝て待てと言うが、ゆっくりと落ち着いた気持ちでいられるわけがない。
- 果報は寝て待てとは言っても、生前は評価されず、死後に評価された人は果たして報われたと言えるのだろうか。
「果報は寝て待て」の類語や対義語はある?
「果報は寝て待て」と同じような意味を持つ類語(類義語)は、下記のような言葉があります。
【1】人事を尽くして天命を待つ
「人事を尽くして天命を待つ(じんじをつくしててんめいをまつ)」ということわざには、
『人間の能力でやれることをやりきったのなら、あとは定められた運命に任せるしかない』という意味があります。
類語の中でも同義語と考えて良いでしょう。
【2】待てば海路の日和あり
「待てば海路の日和あり(まてばかいろのひよりあり)」ということわざには、
『今は状況が悪いかもしれないが、辛抱して待っていれば必ず好機がやってくる』という意味があります。
「海路」とは、海上の船が通る路のことです。
海がひどく荒れていて今は航海ができないないかもしれないが、待っていれば必ず航海に適した穏やかな天候になるということがこの言葉の由来となっています。
ちなみに、このことわざは、「待てば甘露の日和あり(まてばかんろのひよりあり)」と言われていた言葉が「海路」へと言い方を変えて用いられるようになったと言われています。
「甘露」とは、中国の伝説で天が振らせるという甘いつゆのことです。
日照りの日が続いても辛抱強く待っていれば、やがて甘露のような恵みの雨が降る日が訪れるということがこの言葉の由来とされています。
【3】石の上にも三年
「石の上にも三年(いしのうえにもさんねん)」ということわざには、
『どんなに辛くても辛抱して努力していれば、やがて変化が訪れ好転する』という意味があります。
たとえ冷たい石であっても、三年も石の上に座っていれば石も温かくなるということから生まれた言葉ですが、三年というのは、ある程度の長い期間という比喩的表現になります。
成功するためには、諦めずに努力し続けることが大切ということです。
「果報は寝て待て」の対義語
「果報は寝て待て」の対義語は、下記のような言葉があります。
【1】蒔かぬ種は生えぬ
「蒔かぬ種は生えぬ(まかぬたねははえぬ)」ということわざには、
『準備や努力を何もしなければ、良い結果は得られない』という意味があります。
種を蒔くという原因が無ければ、作物が実るという結果は生じないため、努力なしに良い結果を期待しても無駄ということです。
また、「打たぬ鐘は鳴らぬ(うたぬかねはならぬ)」や「物が無ければ影ささず(ものがなければかげささず)」といった言葉も「蒔かぬ種は生えぬ」と同類のことわざになります。
【2】棚から牡丹餅
「棚から牡丹餅(たなからぼたもち)」ということわざには、
『努力や苦労もせずに思いがけない幸運に恵まれる』という意味があります。
「たなぼた」と略した形で用いられることも多い言葉です。
棚の近くで寝ていた時に、棚から落ちてきた牡丹餅が偶然にも開いていた口に入ったことが由来となっていて、予想外な幸運に対して用いる言葉となります。
また、「開いた口へ(牡丹)餅」や「開いた口へ団子」と言われることもあります。
【3】運を待つは死を待つに等し
「運を待つは死を待つに等し(うんをまつは しをまつにひとし)」ということわざには、
『何も努力もせずに幸運が訪れるのをただ待っているのは、自らの死を待つように愚かである』という意味があります。
幸運を得るためには行動が必要で、何もしないで運に期待するのは良くないということです。
「果報は寝て待て」を英語で表現すると?
「果報は寝て待て」を英語で表すと、下記のように表現されています。
『Good thing come to those who wait』
(良いことは待つ人のところにやってくる)
英語圏でも日本と同じように「ことわざ」として用いられているようです。
また、次のような言い方もされています。
『All things come to those who wait』
『Everything comes to those who wait』
まとめ:果報は寝て待てには、幸運の訪れは人間の力ではどうすることもできないのだから、焦らずに時機を待つのが良いという意味がある

- 「果報は寝て待て」は、仏教の思想が由来となって生まれた言葉
- 「果報」は、仏教では「因果応報」と同じ意味だが、一般的には幸運(良い報い)を表す
- 「果報は寝て待て」の類語は、「人事をつくして天命を待つ」・「待てば海路の日和あり」・「石の上にも三年」などがある
- 「果報は寝て待て」の対義語は、「蒔かぬ種は生えぬ」・「棚から牡丹餅」・「運を待つは死を待つに等し」などがある
いかがでしたでしょうか。
「果報は寝て待て」は、幸運が訪れるのをただ待つというのではなく、やれることは全てやった後に、 あとは自然にまかせて静かに良い知らせが来るのを待つしかないという意味で用いられる言葉ということが分かりました。
特に何か行動をするわけでもなく、ついつい「何かいいことはないかな~」と考えてしまいがちですが、スピリチュアル的にはその考えは捨てないと良い運は訪れないそうです。
「何かいいことはないかな~」と思っているということは、今自分が置かれている状況に満足していないということであり、負の思考に偏っていると考えられます。
良い運を呼び込むためには、ポジティブ思考になることが大切とされていて、ささいなことでも良いので毎日の出来事の中から「いいこと」を見つけ、それを「ラッキーなこと」だと実感してみる。
そして、明るく前向きな言葉である「ありがとう」や「嬉しい」、「幸せ」といった言葉を積極的に使ってネガティブな言葉は使わないようにしていくことで、自然と良い運が巡ってくると言われています。
幸運を得るためには、何事も自らが積極的に行動し、ポジティブな思考に変えていかなくてはいけないということですね。
ここまでご覧いただき、ありがとうございました。